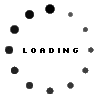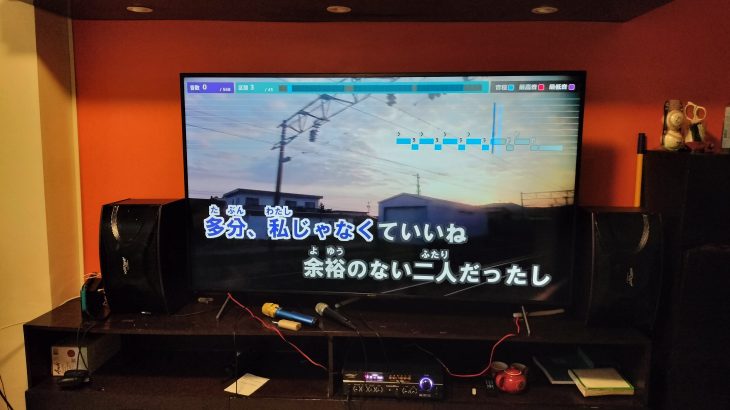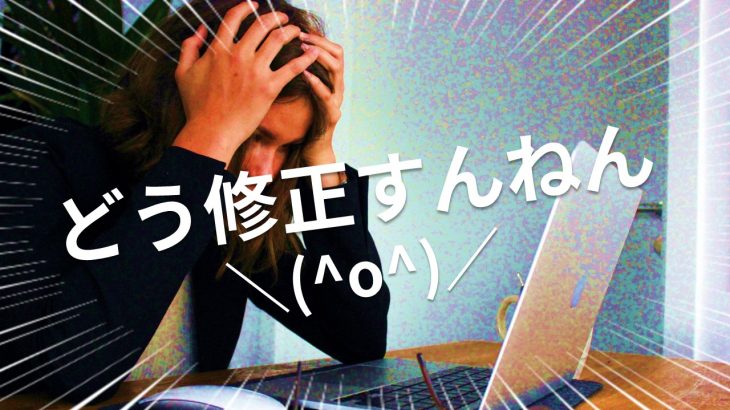こんにちは、セブテク編集部です。
今回はWebサービス・システムなどの開発や運用において、一般的になりつつあるクラウドサービスについてご紹介していきたいと思います。
クラウドサービスとは?
クラウドサービスを簡単に説明しますと、
ユーザーがインフラやソフトウェアを持たなくても、インターネットを通じて、サービスを必要な時に必要な分だけ利用する考え方
ということになります。
システムを構築する際にかかる時間やコストをクラウドサービスを利用することにより、抑えることが可能になります。
例えば、
サーバーを構築したいが、サーバーPCの購入・ハードウェアの設置・ソフトウェアのインストールなどの手間が掛かる作業をクラウドサービスを利用して数分で構築することができたりします。
最近では、2025年までに企業の8割がデータセンターを閉鎖するといった調査結果が、某有名調査企業によって報告されたことが記事になりました。
さらに日本政府は基盤システム(一部)でAWS(Amazon Web Services)を採用することが決定されました。
このようにクラウド化・サーバーレス化といった、脱オンプレの流れは一般的になりつつあります。
代表的なクラウドサービス
では次に代表的なクラウドサービスについて見ていきましょう。
- AWS(Amazon Web Service)
Amazonによって開発されているクラウドサービスになります。 - GCP (Google Cloud Platform)
Googleによって開発されているクラウドサービスになります。 - Azure
Microsoftによって開発されているクラウドサービスになります。
これらのクラウドサービスにはそれぞれ特徴や制限があるため、ニーズに合わせたサービスを選択することが重要になります。
最近ではマルチクラウドといった、いくつかのクラウドサービスのいい部分を組み合わせて運用するといった方法も浸透しつつあります。
安全面はどうなの?
クラウドービスはとても便利でコストパフォーマンスもいい!
でも災害時などの対策はどうなっているの?
データやサーバーの運用をクラウド上で管理するとなると、その辺りも気になりますよね。
しかし、ほとんどのクラウドサービスでは冗長化を行うことができます。
例えば、AWSでは各リージョン毎にAZ(アベイラビリティゾーン)というものが用意されています。このAZはそれぞれ別の場所に用意されていることから、 AWSによるベストプラクティスに沿ってサーバーやデータベースをそれぞれのAZで構築することにより、一つのAZで障害が起きた際でも別のAZで運用を続けることができます。
これはオンプレでの運用をする際では実現が難しいですよね。
しかしクラウドサービスを使うことにより、比較的容易に実現するることができます。
さらにAWSではサーバー構築などの手順をテンプレート化することができ、そのテンプレートをユーザーが定めた条件下で使用することができます。
これにより、サーバー上でエラーが生じた際には別のサーバーを自動的に構築し、ユーザーアクセスを新しく構築されたサーバーへ変更することもできたります。
料金について
料金につきましては、ほとんどのクラウドサービスでは従量制となっております。
使用する規模にもよりますが、しっかりとそれぞれのクラウドサービスを勉強し使用することで、多くの場合では比較的金額を抑えることができます。
例えば、AWSを利用してサーバーを1年間運用したい場合
AWSの提供しているリザーブドインスタンスを使用し、1年分のクラウドサービスの利用金額を先払いすることで、本来の利用金額が最大75%割引されます。
クラウドサービスを使用する際には、使用するクラウドについて深く理解し、利用者のニーズに合わせた選択が重要になってきます。
まとめ
いかがでしたか?
今回はクラウドサービスを利用することのメリットについて述べてきました。
クラウドサービスを利用することで、運用するシステムのコスト面・可用性を最適化することが容易になりつつあります。
これから新しくシステムやアプリを開発したい・今あるシステムをより効率的に運用していきたい!
と考えている方は、クラウドサービスのご利用を検討してみてはいかがでしょうか?